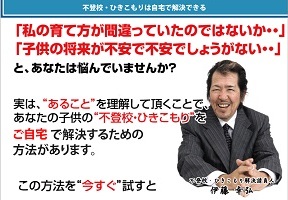[必読]伊藤幸弘・不登校ひきこもり解決
私は以前東京で学習塾を経営していた関係で、中学生や高校生の勉強の悩みはもちろん、彼らの「心の悩み」についてもずいぶんと相談に乗る機会がありました。
それだけに、自分では聞くつもりはなくても、自然とそういう関係の話が耳に届いてしまうという部分も多分にあったと思います。
あるとき、「保健室登校」ということばを耳にしました。
いわゆる「不登校」の前触れでもあり、また「不登校」の顛末でもあるというある状況を指すことばなのですが、まあこれはもちろん、「学校に行くことは行くが、勉強についていけない、あるいは教室の雰囲気になじめない」などという理由から、
という、学校からすればある種の特別扱いを容認した形であるとも考えられると、そのときはちょっと思いました。
私の教室はとても規模が小さかったということもあって、幸いにもそのときには不登校に悩む子どもも保健室登校をという選択に迫られた子どももいなかったので、そのときには、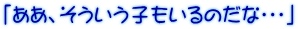
と、漠然と考えるにとどまりました。
この「保健室登校」というのは、多くは「自習プリント」を黙々とこなし、わからないところがあれば、時おり回ってきた先生に質問する、というシステムなのだそうです。
しかし、ある意味そんな理想的な勉強が成り立つのであれば、保健室登校などという中途半端な形に甘んじることなんてないのにな、などと正直考えてもいたのです。
当時、私のところには10人足らずの中学3年生、10人ちょっとの中学2年生がいて、その他は小学生と高校生が少しずついたというメンバー構成の教室でしたが、いよいよ受験生の勝負も大詰めにさしかかっていたというタイミングで、ある事件が起こりました。
それは、通っていた中学2年生のひとりの男子にまつわる「事件」だったのです。そのお母さんが、昼間、だれも生徒がいないときに、突然教室にやってきました。
受験生のお母さんが居ても立ってもいられなくなって相談しにくるということは、それほど頻繁ではないにしろ、それほど珍しいことでもなかったのですが、しかし2年生の母親ともなると、それは実に珍しいケースだったとは言えます。
私は少し警戒しながらあいさつをし、何の話なのかと少々身構えていたのですが、お母さんの話は、私の想定をはるかに超えるものでした。お母さんは言いました。
何でも、理由も一切言わないし、体調が悪いわけでもない、ご飯も食べる、しかし学校にはどうしても行きたくないと、その一点張りだったのだそうです。
その子は、確かにちょっと変わったところがある子ではありましたが、私が多少厳しく接しても、正しいことを理解することができる子ではありました。
要するに、一般的に見れば、どこにも問題はなく、友だちもそれなりにいるような「普通の子」だったのです。
関連記事

原因を探る
(彼の件に関して言えば)幸い、血気の多い受験生は他人のことにかまっていられない時期に差し掛かっていましたし、教室に通っている同級生たちは男女とも「幼馴染」に近い間柄だったため、以前ほど積極的ではないにしろ、私の授業には比較的よく足を運んでくれていたのです。
しかし、それも徐々に減り、昼間の空いた時間にだけ「特別にお願いします」というお母さんの申し出があり、やむを得ずこれを受け入れることにしたのです。
1対1の授業ということで、これは非常に珍しいケースだったのですが、しかしそれだけ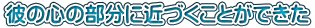
というのは紛れのない事実でした。つまらない冗談を言っても、これまでと同じように笑顔を見せ、それほどまだ深くまで傷ついていないように私には感じました。
そうした「特別授業」をはじめて、一番厳しい受験もなんとか乗り越えることができ、ほっとひと息というタイミングで、私は彼に
と訊いてみました。実は、私は彼には一切内緒にして、彼と仲が良い友だちにいろいろ探りを入れていたのですが、どうやら彼本人からこれに関しては口止めされていたようで、いくら訊いても「わからない」、心当たりも「ない」の一点張りだったのです。
彼は私に訊かれてちょっとハッとしたような表情を見せましたが、すぐに視線を下に落としました。私は詰問するつもりはなかったのですが、もうひと押しだけしてみようと思い、さらに質問を続けました。
すると彼は、「○○○って知ってる?」と、逆に私に訊いてきたのです。何か英語のような、人の名前のような、とにかく不思議な響きだったのですが、いずれにしても私はまったく聞いたことがないことばでした。
彼はとてもアニメが大好きな少年であり、これはいわゆる「アニメオタク」という種類の属するのかな、と漠然と感じてはいたのですが、その「○○○」というのは、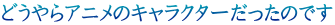
彼の話では、そのアニメのキャラクターの名前をあだ名にされ、からかわれたことがショックであり、その結果、学校に行きたくなくなったというのです。
まあこう言ってはナニなのですが、非常に幼稚な理由で「不登校」という選択肢をたどったというのです。
その夜、私は教室に来た彼の友だちのひとりに、かの「○○○」といのを知っているかと訊いてみました。彼もアニメが大好きで(というか、そのつながりで仲良くなった?)あり、彼はもちろん知っているという風情で得意顔をして「はい」と言いました。
私はそれがどんなキャラクターであるのか説明するように言うと、どうやらそのキャラクターの説明はとても難しいらしく、彼は戸惑っていました。
しかし、そのキャラクターに関するやりとりをしたところで、他の生徒はまったく無関心を装っていたため、私は何かおかしいと、
というのも、もしもそれが原因で彼が不登校になったのだとすれば、友だちか他の生徒が何らかのリアクションを示すと考えたからです。
関連記事

意外な情報
春休みに入りましたが、例年入試が終わったばかりということもあり、また短い休みでもあるという理由から「春期講習」は行わないのですが、その年は講習をやってほしいという要望があったために、正直イヤイヤ行うことにしました。
その要望があった子が、午前中にただひとりだけ講習を受けにくるという機会に恵まれました。
その子は小学生のころから私の教室に来てくれていて、女子中学生にしては非常に冷静沈着でマイペース、浮ついたところがほとんどない(というか、ポーカーフェイス)なところがあって、比較的口がカタい印象があったため、かの不登校の男子(同級生)の話を思い切ってしてみました。
バーベキュー会を開くということを条件に当然「内密」の約束を取り付け(なんてヤツだ!)、例のキャラクターに関することで悩んでいるみたいだ・・・ということを彼女に説明したのですが、彼女は私の話を途中で遮り、そしてこともなげにこう言いました。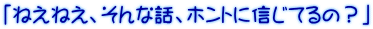
アホじゃないの?という顔で見上げる小柄な女子を見降ろしながら、私は「やられた!」と心の中で地団太を踏みました。
彼女はため息交じりでおもむろに話し始めました。
実は、彼は先天的に股関節に障害があり、歩く分には見ていても違和感はないものの、しかし気の毒にも、体育の授業や遠足などは必ず見学または欠席しなければならなかったのです。
彼女は「絶対にナイショだよ」と前置きして、話を続けました。
確かに中学3年生になる男子が、ちょっとからかわれたからと言ってそんなに傷つくものなのか、私には判断つきかねてはいたのですが、しかし何か「おかしい」という印象は正直ありました。
彼女の話によれば、夏、プールの授業のときに、見学を抜け出して女子更衣室に潜入し、女子の下着を物色したという、
しかも悪いことに、それを彼と仲が良かった男子に目撃されてしまい、その秘密を冬になっていわゆる「いじめっ子グループ(不良グループ)」に握られてそれを広められてしまい、相手が相手だけに何も言い返すことができないまま不登校に至ってしまった・・・という経緯でした。
私は彼女に訊きました。彼は本当にそんなことをすると思う?彼女は、「それはわかんないど、他の男子に言われても言い返さないんだからそう思われてもしょうがないじゃん・・・ってか、クラス違うし、あたしアイツに興味ないし」と、そう言いました。
確かに、言い返さなかったがうまくなかったのは事実でしょう。
しかし、「言い返していたらもっとひどい目に遭わされていたかもしれない」という恐怖が彼の中にあったことも事実のはずです。
講習を終え、昼飯を食いながら私は考えました。それは確かに親にそんなことを言えるはずもなく、私に質問されるたびに一連のツラいできごとを思いださなければならないというのは、それが事実であろうとそうでなかろうと、彼が置かれたあまりにも苦しい状況を思うと居たたまれない気持ちになりました。

逆鱗に触れるのを恐れて
考えてみれば、彼は同い年の男子の逆鱗に触れるのを恐れて「不登校」という選択肢を歩んだわけですが、彼も当然進路のことが頭に入っていないわけではありません。
彼のお母さんとも話を重ねましたが、彼は学校には行きたくないとい言い続け、そして学校の先生も、「もし無理をして大ごとになってしまったら大変だから」という、まるで彼が学校に行かないことが先生にとっては「大ごと」ではないと考えているかのような不思議な言い方で、「学校に来られないのは仕方がない」という見解を示しました。
しかし内申については、学校にさえ来ていれば、テストがすべて「0点」であってもそれぞれの教科で「1」がつくものの、学校でテストを受けない以上は、「1」さえつけることはできない(つまりは、「オール1」よりも低評価となる)ということだけは覚悟してくださいと言われたのだそうです。
私はその話を聞いて、学校の教師というのはずいぶんとラクな仕事なのだなと、そのとき思いました。とすると、「不登校」という状況をどう打開するか!焦点はただそこに絞られたことになることを私は理解しました。
彼を説得するためには、その手法としてやはり事実関係を知らなければならないと一瞬考えたものの、彼をそれ以上傷つけることだけは私にはできず、幸い私は警察の人間ではないので、彼は「あだ名で不登校になった」と思いこむことにしました。
3年生に入り、大事な1学期を「不登校」という形で終えようとしていました。そして夏休みに入って早々、いよいよ彼とそのことについて1対1で話さなければならない日がやってきました。
いくら話しても聞く耳を持ってくれないから、何とか先生のほうから説得をお願いしますという申し出があったのです。
私はまず、彼が都立高校の志望ということで、都立高校の入試制度についてできるだけ詳細を説明しました。そして彼に「今のままだと内申がまずいことになるのは理解できているのか」という質問をしました。
すると彼は「定員割れしている学校に行くからいい」と言いました。定員割れしてれば全員合格できるものと考えていたのです。
それは間違いであるという認識を諭すと、今度は「それならば高校なんていかない」と、そう言いだしました。
高校に行かないでどうする?と訊くと、彼は、もう先のことなんて考えたくない、とにかく学校には行かない、友だちなんていらないし、高校なんて行く必要はないと言いました。
そして最後に、「家族がいればそれでいいよ。先生になんて俺の気持ちはわからないよ」と、どこか投げやりに彼は言いました。
私は無性に腹が立ちました。彼のことばの内容や、ことばのトーンや、そんなこととは別に、どうして彼だけがこんなに苦しい思いをしなければならないのかと、そんなふうに感じたのです。
もちろん、原因は彼のほうにあるのかもしれないけれど、それにしてもどうして彼にはこんなに味方が少ないのだろうと思うと、なぜか無性に腹が立ったのです。
ああわからねぇよ!お前の気持ちなんてわからねぇ!俺はお前とは他人だ!アカの他人だ!わかるはずがなねぇんだよ。
でもよく考えろ、君の本当の苦しみを君の家族の誰が理解している?どうしてこんなことになってしまったのか、その本質を君の家族の誰が理解しているんだ?
関連記事

家族の理解
私の怒鳴り声を聞いてはじめはびっくりした顔をしていましたが、そのあとすぐに彼は自分の足元をじっと見つめました。
だれかがストップをかけなければいつまでもそうしているのではないかと思われるくらい、彼はうなだれたままじっと「何か」を見つめていました。
いや、その「何か」がどんなものであれ、私は彼がしっかり目を見開いて、なんでもいいから「何か」を見ていてほしい、見ることだけは拒まないでほしいと、そう願いました。
さすがに少し言い過ぎたのかもしれないと、私は少し後悔しました。しばしの空白のあと、彼はうつむいたまま誰にともなく言いました。「家族も・・・家族も俺のことを本当に理解していないんですか?」
私は逆に訊きました。「それなら、君は家族のことを本当に理解してる?表面的な理解ではなく、本質を理解しているのか?もし理解しているのなら、君は『不登校』なんていう道は選ばなかったと俺は思うよ」
私は言いました。「君は、今まで家族に守られてこれまで生きてきた。でも、いつしか君にも家族ができて、今度は君が家族を守ることになる。
そのとき初めて君は、今の君のお父さんやお母さんの『本当の気持ち』を理解することになるんだと思うぞ」
彼は顔を上げて、少しぼんやりした表情で私の顔を見ました。古めかしいクーラーの室外機の音だけがけたたましく聞こえてきました。
「今はいろいろつらくて、遠回りしてはいるけれど、君にとってこの経験は今後大きなプラスになる。理解できなくても、理解しようと精いっぱい足掻いてみろよ。何か見えてくるかもしれないぜ」
夏休みを終え、いよいよ勝負の2学期に突入し、気が引き締まるのを感じていました。他の受験生たちは順調に足固めをし、これからいよいよ本格的な入試問題に取り組む時期に入ってきました。
例の生徒も、特別何も言いませんでしたが、夏期講習の延長という感じで、2学期に入っても昼間に勉強をしにくるというサイクルは相変わらず続いていました。
しかし、私の知らない間に事態は急転していたのです。
2学期に入ってまだ1週間も経たないときに、彼のお母さんがまたひょっこり教室に顔を出しました。
夏休みに1対1で話をしたことに関しても、「正直これで何かが変わるとは思えない」というような否定的な見解をお母さんにお話してはいたのですが、これ以上彼の不登校のことに深くかかわりすぎて他の生徒の受験に影響が出てしまうことを私は恐れました。
何しろ、そういう経験はこれまで一度もなかったから、ただ不安だったのです。するとお母さんは言いました。「先生ありがとうございます」と。
私は何を言いたいのかがよくわからなかったのですが、聞くと、彼は自分から「学校に行くようにする、でも教室には行きたくないから保健室でやる」ということをお母さんに告げたのだそうです。
彼はいわゆる「保健室登校」という新しい道を模索したのです。
彼は結局卒業まで保健室登校を続け、定期テストだけは教室で受け、他の生徒同様数値化した成績をもらい、無事都立高校に入学することができました。私の知る限りでは、優秀とは言えないまでも、